今回は「薬剤師は医療行為を行えない?過去の通達と在宅医療の現場から考える」をテーマに話してみます。
—
こんにちは。「キッサ薬局」の店主です。
薬局薬剤師をしています。これが初投稿になります。
いろいろ不勉強もありますが、気になること発信していけたらと思います。
—
「薬剤師は医療行為ができない」
これは一般的に知られていることかもしれません。
実際、医師法第17条では「医師でなければ医業をなしてはならない」と定められており、
原則として医療行為は医師のみに認められています。
しかし、厚生労働省からの通知や現場の運用を通じて、
“薬剤師でも一部の行為が許される”という解釈が広がってきた例もあるのをご存じでしょうか。
—
【薬剤師の“医療行為”が解釈上認められた例】
たとえば平成26年、厚生労働省から
「薬剤師が、調剤された外用薬の貼付、塗布又は噴射に関して、医学的な判断や技術を伴わない範囲内での実技指導を行うこと。」
という通達が出されました。
これは、患者が塗布方法に不安を感じている
使用法を説明するために一度実演する
というケースにおいて、治療目的ではなく指導目的の行為として容認されたものです。
また、吸入指導においても
「吸入デモ機を用いた操作指導は服薬指導の一環であり、医療行為に該当しない」と解釈されています。
—
【在宅医療の現場で見える“薬剤師の可能性”】
さらに、在宅医療の現場では
薬剤師の関わり方がますます重要になっています。
例として「PCAポンプ(自己調節鎮痛ポンプ)」の操作があります。
本来、PCAポンプの操作は医師や看護師が担うものでした。
しかし、在宅では看護師や医師が毎回立ち会えるわけではありません。
このような状況で、
「医師の指示のもと、薬剤師が機器の準備や操作補助を行う」
という運用が行われるケースが増えています。
もちろん、法的には「投与開始・投与量調整」は医療行為にあたるため行えませんが、
「薬液の補充」を医師の指示通りに行い、詰めた物を他の医療従事者へ渡すのみ、
に終始してしまうだけでよいのでしょうか?
【薬剤師が在宅医療に関わる意義】
このように、
「医療行為」の枠組みが厳密でありながらも、
患者さんの生活の場に近い場所で薬剤師が関わる必要性が高まっているのが現状です。
薬剤師が在宅医療で、適切な服薬指導、薬剤管理、機器の補助的な操作
を担うことで、
「患者の安心感」や「医療従事者の負担軽減」に繋がる未来が見えます
【介護職は目薬を点せる?】
介護士も原則として医療行為は薬剤師と同じくできません。
しかし、一部「医療的ケア」として、医薬品使用の介助として介護士もできることがあります。
- 一包化された内服薬の内服
- 湿布を貼る
- 軟膏を塗る
- 目薬の点眼
- 座薬の挿入
- 鼻腔粘膜への薬剤噴霧
は、条件を満たしていれば介助を行うこと可能との旨が
令和2年2月の厚労省からの通知で記載されており、これを根拠に現場では行われているようです。
これは、、、薬剤師のやっていいのか?けど薬剤師法への記載はないし、、なかなか厳しそうですね。
【まとめ】
薬剤師は法律上、原則として医療行為を行えません。
しかし、厚生労働省からの通達や現場の運用を通じて、
「服薬指導の範囲内」「医師の指示下」という条件のもと、
一部の行為が解釈上許されるケースが出てきました。
在宅医療が今後増えていき、医療資源がどんどん減っていく中、
薬剤師も行ううべき医療行為はどんどん増えていくと個人的には感じています。
そして薬剤師の役割は今後さらに重要になっていくでしょう。
キッサ薬局では、これからも気になった事をなんでもテーマにとりあげ
色々と発信していきたいと思います。
【参考資料】
厚生労働省 各通知

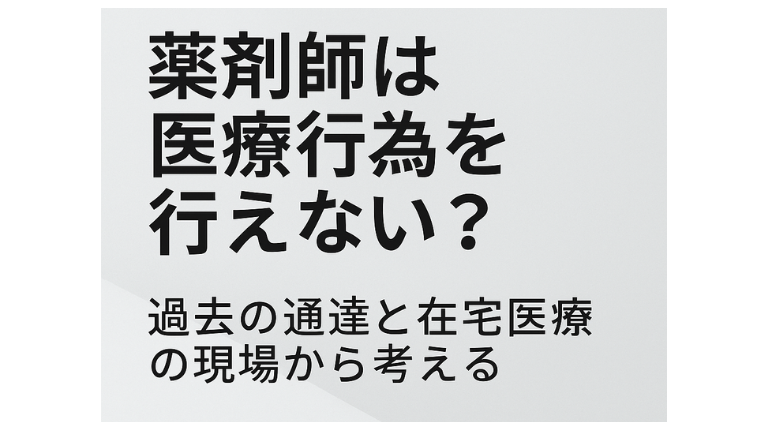
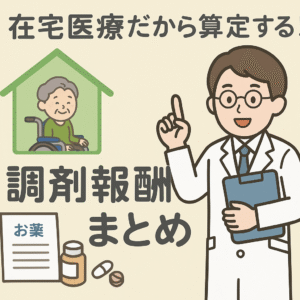
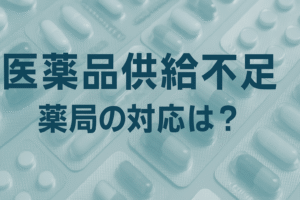
コメント